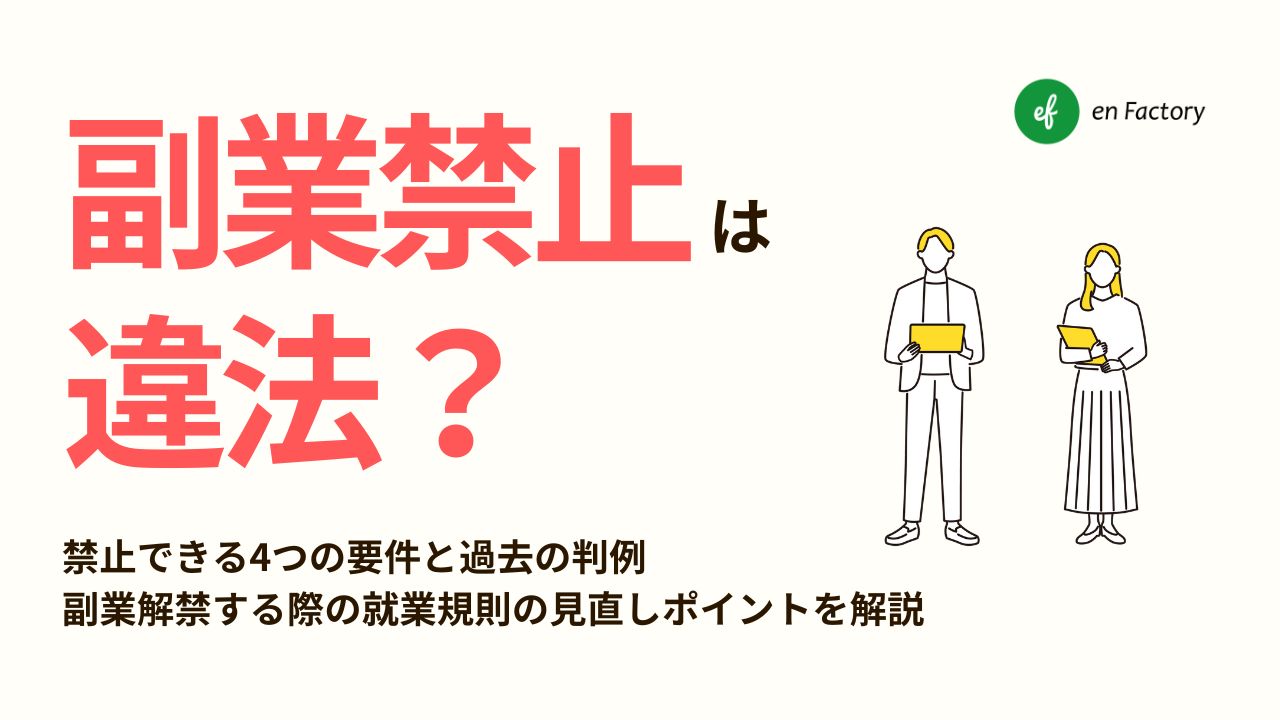副業解禁の流れが進む昨今、就業規則で定められた副業禁止規定が無効と判断されるケースが増えています。
しかし、企業としては社員の副業に関して何らかの線引きを設けたいのも事実。企業の定める副業禁止規定は、法的にどこまで有効なのでしょうか。
本記事では、厚生労働省が示した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」をもとに、企業による副業の制限が認められるための条件をわかりやすく解説します。副業に関する過去の判例も紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
目次
就業規則で副業を禁止することは違法?
副業禁止の就業規則は、必ずしも法的に有効とは限りません。最近では副業を容認するべきという考え方が主流になりつつあるため、一律での副業禁止には注意が必要です。
まずは、副業の制限に対する基本的な考え方を解説します。
勤務時間外の活動を一律で制限することは原則として難しい
結論から申し上げると、社員による副業を一律で制限することは、原則として難しいと考えるべきです。「勤務時間外の社員の行動は原則として自由であるべき」という考え方から、副業を一律で禁止するための就業規則は無効と判断される可能性が高いです。
厚生労働省が2018年に公表した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、副業の制限について以下のように言及しています。
裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。 副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に 支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、そのような事情がなけれ ば、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業 を認める方向で検討することが求められる。
(厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドライン「3. 企業の対応」より引用)
このガイドラインの内容からもわかる通り、企業は社員の副業を基本的に認める方向で調整することが求められています。
それでは、企業が社員の副業に対して制限をかけることはできないのでしょうか。
実は、同ガイドラインの中には副業禁止が有効なケースもいくつか述べられています。詳しい要件は後ほど詳しく解説しますが、重要な点は「一律で」副業を禁止することは難しいということです。
正当な理由があれば従来通り企業は社員の副業を制限できますが、これはあくまでも「例外」として取り扱う必要があるということになります。
参考:厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドライン
昨今は副業を解禁する企業が増えてきている
働き方改革の影響によって、最近は副業を容認する企業が増えていています。経団連が公表した調査によると、副業を容認する企業の割合は次のように推移しています。
| 年度 | 副業の容認率※ |
| 2018年 | 41.4% |
| 2019年 | 46.0% |
| 2020年 | 50.6% |
| 2021年 | 60.9% |
| 2022年 | 83.9% |
※社員数5,000人以上の企業のうち、副業を「認めている」「認める予定」と答えた企業の合計
参考:一般社団法人日本経済団体連合会 副業・兼業に関するアンケ―ト 調査結果
特に2021年から2022年にかけての推移は顕著です。調査対象が大企業のみではありますが、実に10社中8社以上が社員の副業を認めている計算になります。中小企業にも副業容認の流れは波及しており、今後も副業を容認する企業はますます増えるでしょう。
公務員は副業が法律で禁止されている
副業容認の流れが広がっていることを紹介しましたが、公務員の場合は2025年時点でも法律によって副業が原則として禁止されています。
例えば国家公務員の場合、国家公務員法では次のように定められています。
職員は、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
(国家公務員法 第103条)
特別な許可がある場合や自営業の場合などの例外はありますが、国家公務員による副業は事実上ほとんど禁止されているのが現状です。地方公務員も同様に、地方公務員法第38条によって副業が原則として禁止されています。
こうした規則の目的は、主に公務員の中立性を確保することです。また、公務に専念してもらうことや、行政機関としての信頼性を維持することも目的の一つとされています。
ただし、2025年6月には総務省が地方公務員の副業をより柔軟に認めるための「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」を発表するなど、最近では公務員にも副業を容認する動きが広がりつつあるのも事実です。今後、こうした流れが加速する可能性も十分にあるでしょう。
副業を禁止できる4つの要件
企業が社員の副業を制限できるのは、以下の4つのケースです。
- 事業が競合する場合
- 業務の秘密保持が必要な場合
- 本業に支障をきたす場合
- 信頼関係が破壊される場合
ここからは、企業が社員の副業を禁止できる4つのケースを解説します。
なお、これらの基準についてより詳しく知りたい方は、以下のページから弊社エンファクトリーのご用意する「副業解禁ガイドブック」をご覧ください。弁護士監修のもと、副業禁止が認められる要件や実際の企業事例といった副業解禁に役立つ情報を詳しく解説しています。はじめての副業解禁ガイドブック | 越境学習のご案内
参考:厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドライン, 副業・兼業の促進に関する取組について
事業が競合する場合
本業と副業で事業が競合する場合、企業は社員の副業を禁止できる場合があります。極端な例ですが、「勤務先と同じ顧客を相手に副業で別の商材を売り込む」といった行為は、企業と利益相反が生じるため、禁止が有効と認められる可能性が高いです。
ただし、単に「同じ業界での副業」「似たような職種での副業」というだけで競合と認めてもらうことは難しいでしょう。裁判所は、市場規模や地域性などを総合的に考慮したうえで個別に判断するため、企業側もケースバイケースで可否を判断する必要があります。
実際、副業を解禁した企業の中には、「同業での副業を一律禁止とはせず、上長や人事部がその都度判断する」といった仕組みを設けている事例が多いです。
業務の秘密保持が必要な場合
秘密保持が必要な場合も、企業が社員の副業を禁止できる可能性が高いです。
社員が業務で知りうる「秘密」としては、例えば以下のようなものが挙げられます。
| 研究職・技術職 | 技術のノウハウ、特許などの情報 |
| 営業職 | 顧客や取り引きに関する情報 |
| マーケティング職 | 新商品やサービスの情報 |
こうした情報が流出すると企業の競争優位性が損なわれかねないため、これらの流出が懸念される場合は社員の副業を制限することが認められています。
ただし、副業を制限するうえで合理的なほどの懸念が生じるかどうかは個別での判断が必要です。少なくとも、企業は「具体的にどの情報がなぜ機密なのか」「その情報が漏洩すると企業にどのような損害が生じるのか」を具体的に説明できるようにしておくことが求められます。
本業に支障をきたす場合
本業に支障をきたす場合も、企業は社員の副業を制限できます。
具体的には、次のようなケースです。
- 総労働時間が過度に増え、業務品質が低下する
- 遅刻や早退、欠勤が増える
- 疲労によって事故が誘発される
上記に該当する場合、就業規則などに定められている職務専念義務違反などに該当する可能性があるため、社員の副業を制限することができます。
なお、企業側としては社員が副業に費やす時間をあらかじめ把握しておくことが重要です。あまりにも時間が長い場合には、必要に応じて副業の時間の短縮などを求めましょう。
信頼関係が破壊される場合
副業の内容が社会的に問題視されるようなものである場合、社員の副業を禁止できます。
例えば、性風俗店で働くような場合や、反社会的勢力との関わりが疑われるような副業を行う場合です。また、詐欺などの違法性がある場合や、極端な政治活動に関わる場合なども、企業との信頼関係の破壊を理由に副業を制限できます。
社員がこれらの副業に従事すると、会社としての信用が失墜しかねません。そのため、こうした副業を制限することは一般的に認められています。
副業・兼業に関する過去の裁判例
副業や兼業の制限に関する考え方を理解するためには、過去の裁判例が参考になります。ここからは、過去に副業や兼業の制限が問題となった裁判例を3つ紹介します。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000501301.pdf
私立大学教授の懲戒解雇を無効とした判例
私立大学の教授が、大学の許可を得ずに他大学で非常勤講師として勤務していたことを理由に懲戒解雇処分を受けた事例です。
本事例では、裁判所が「大学側による懲戒解雇は無効」と判断しました。判決では、副業が本務のパフォーマンスや職場秩序に対して大きな支障をもたらしていないため、「兼職を禁止した就業規則の条項には実質的には違反しない」としています。
タクシー運転手の懲戒解雇を無効とした判例
タクシー会社の運転手が、就業時間外に船積みのアルバイトに携わっていたことを理由に懲戒解雇された事例です。裁判所は、「直ちに懲戒解雇することは許されない」という判断を示しています。
本事例の運転手は本業に隔日で勤務しており、船積みのアルバイトは非番の日に月7〜8回程度行っていました。裁判所は、タクシー運転手は勤務日の前日に休息が必要であるといった事情から「就業規則により禁止された兼業に該当する」という判断を示しつつも、現実の労働に影響があったことをうかがわせる資料はない点を指摘しています。また、具体的な注意をせず直ちに解雇した点も問題視しました。
建設会社社員の懲戒解雇を有効とした判例
建設会社の社員が、キャバレーで無断勤務したことを理由に解雇された事案です。本件では、裁判所が「解雇は有効である」との判断を示しています。
問題となった社員は毎日6時間以上、深夜までキャバレーで勤務していました。裁判所はこの点に関して、「企業の対外的信用・体面が傷つけられる」「労務提供上の支障や企業秩序へ影響が生じる」といった点を指摘しています。
副業禁止はデメリットが多い
ここまで解説した通り、企業側は社員の副業に制限をかけづらいのが現状です。そもそも、社員の副業に制限をかけることは、本当に企業のためになるのでしょうか。
VUCA時代とも言われる昨今、副業の制限にはむしろ企業側のデメリットが多くなってきています。代表的なデメリットは、下記の3点です。
- 「伏業」につながるリスクがある
- トラブル発生時の対応が事後的になる
- 社員の成長機会を奪う可能性がある
「伏業」とは、社員が企業に無断で副業を行うことです。厳しい副業制限を設けた場合、社員は「どうせバレないだろう」といった気持ちから、企業に隠して副業を行う可能性があります。こうした伏業は大きなトラブルにつながりやすいですし、何かあった場合にも企業側の対応が後手に回りがちです。
さらに、副業禁止は社員のスキルアップの機会を奪うことにもつながりかねません。社員が社外で仕事に取り組むことは、社内にないノウハウを取り込むチャンスでもあるのです。
副業は原則として認めつつ、「事業が競合する場合」「企業の信頼を損なう場合」などの例外的なケースに限って制限することがおすすめです。
副業を解禁するには?解禁に向けた3つのステップ
現時点で社員の副業を厳しく制限している場合、徐々に副業解禁に向けて舵を切る必要があります。
しかし、副業を解禁する際には、単に自社の就業規則を見直せば良いというわけではありません。せっかく副業を解禁するのであれば、自社にメリットをもたらせるようにさまざまな工夫を凝らすことが大切です。
副業解禁を成功させるためには、下記の3つのステップで進めましょう。
- 副業・兼業の目的を明確化する
- 制度を整える(就業規則・許認可ルール)
- 組織全体に学びを広げる
まずは副業・兼業の目的を社内で明確化し、これらによってどのような効果を狙うのかを検討します。その後、目的に沿う形で制度を整えましょう。制度を形骸化させないためには、副業の成功談を社内でシェアしてもらうなど、組織全体に学びを広げるための取り組みも重要です。
これらの手順は、弊社エンファクトリーの作成した「副業解禁ガイドブック」で詳しく解説しています。自社にメリットをもたらす副業解禁を実現したい方は、ぜひこちらのガイドブックをご覧ください。
まとめ
副業禁止の有効性について、政府の方針や過去の判例などを中心に詳しく解説しました。
2018年の「副業元年」以降、副業を解禁する企業は大幅に増加しています。同時に、企業側による一律の副業禁止に対しては、厳しい目が向けられる機会が増えました。2025年に入ってからは公務員でも副業容認が部分的に進むなど、副業解禁の流れはさらに加速しつつあります。
今まで社員の副業を厳しく制限してきた場合は、ぜひこの記事を参考に自社の基準を見直してみてはいかがでしょうか。副業解禁に向けたステップや企業事例は下記のガイドブックでもさらに詳しく解説しているため、ぜひこちらも参考にしてください。