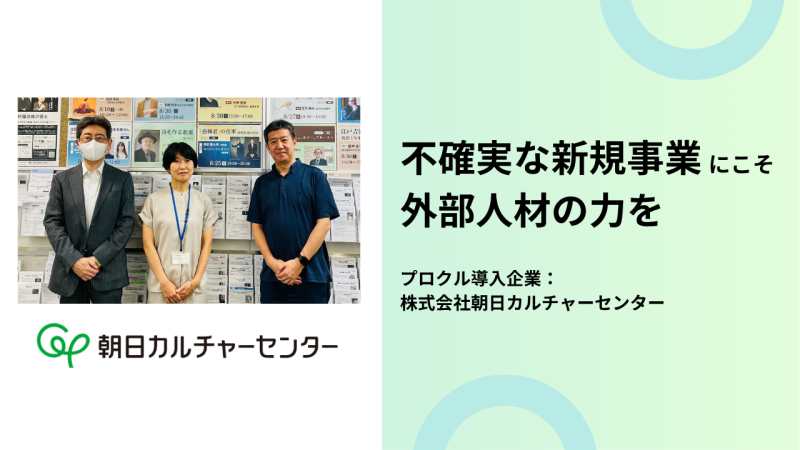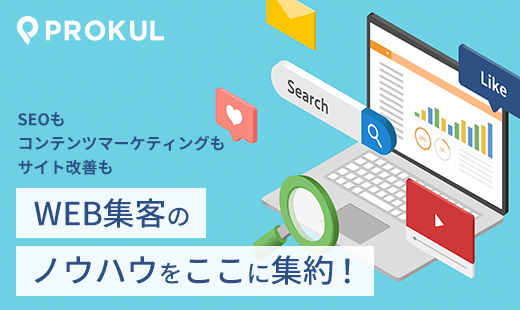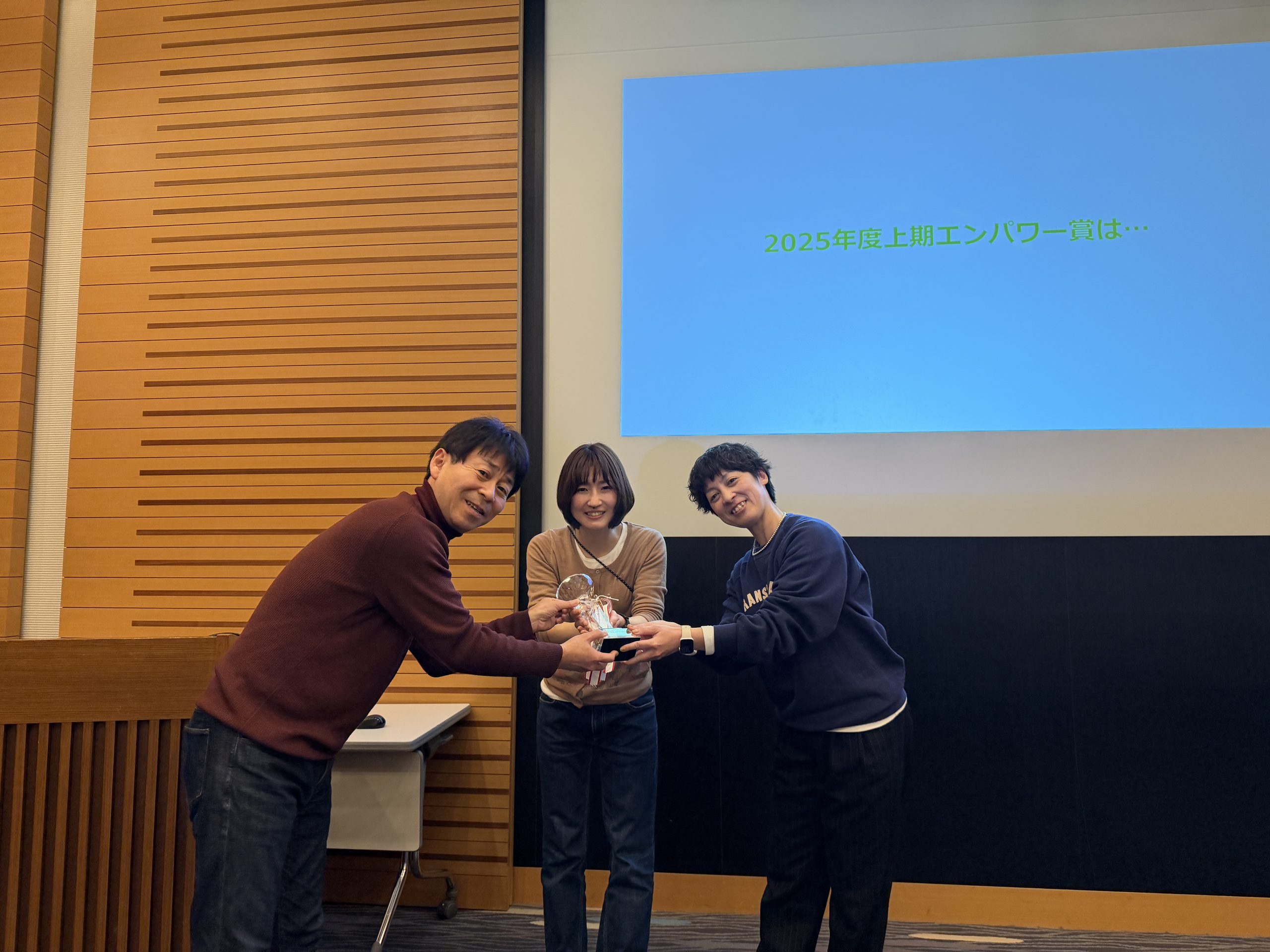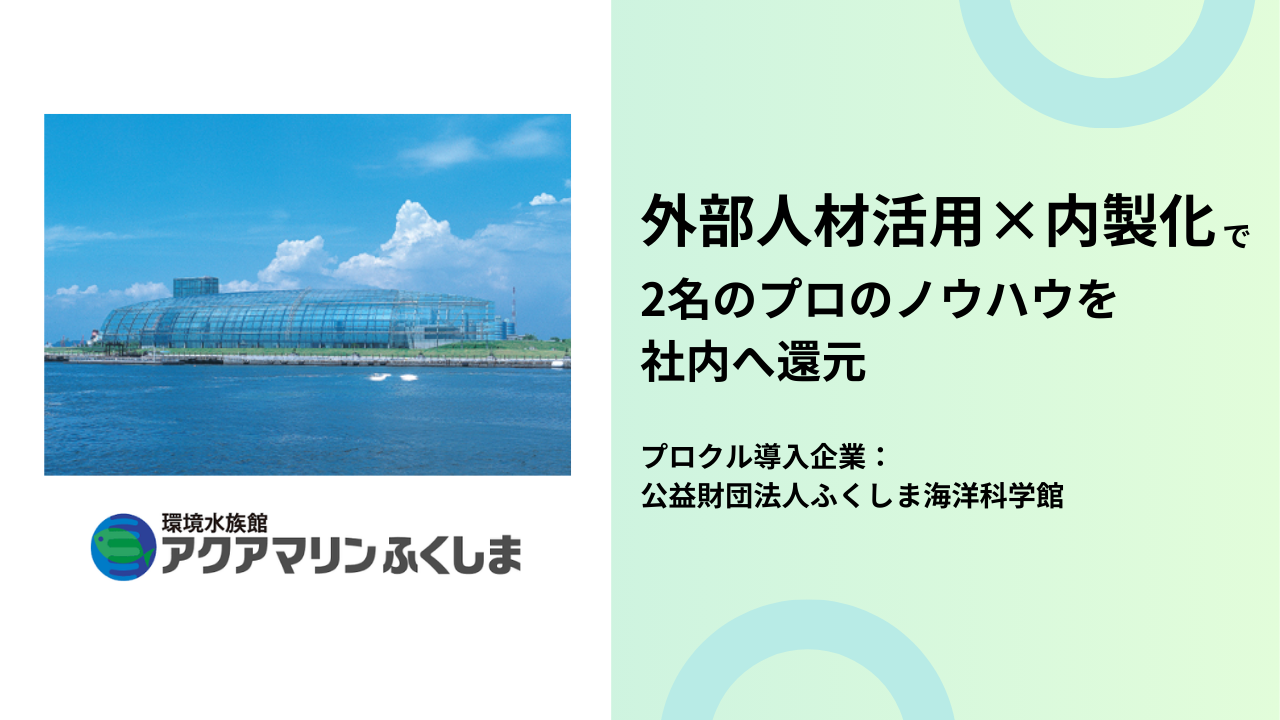今回は、外部人材活用サービス「プロクル」を導入された朝日カルチャーセンターの三橋様(執行役員 事業担当 兼 事業本部長)と、徳田様(事業本部 事業部 課長)に、その具体的な活用方法と得られた成果についてお話を伺いました。
Q:「プロクル」を導入する前の課題について改めて教えてください。
三橋様:
新しい事業を始めるにあたり、とにかく新しいことをやらないといけないという強い思いがありました。その中で、特に大きな課題として直面していたのが、営業リソースの不足でした。
そんな時にたまたま慶野さん(プロクルの事業責任者)にお会いしました。もともと“自前主義”で社内の人間だけで賄おうとしており、その時に初めて「外部人材活用」という手段を検討することになりました。
Q:数ある営業支援サービスの中で、「外部人材活用」そして「プロクル」を選んだ理由を教えてください。
三橋様:
正直言うと、当初「プロクル」に大きな期待はしていませんでした(笑)
うまくいかなければ、途中で解約すればいいか…くらいの温度感でしたね。
ですが、新規事業ではリスクを取る必要があると考えていました。
プロクルの慶野さんのスピーディーな対応が、求めていた営業リソースや動き方のイメージに合致。特に「地方自治体への豊富な営業経験を持つプロ」という具体的な人材像が見えたことが決め手になりました。
パッケージ化されたサービスではなく手探りで事業を共に創るという点が、私たちの状況にフィットしたと感じています。実際に、ご紹介いただいたプロの方の細やかなサポートや親身な姿勢が、当初3ヶ月の予定が1年半という長期的な関係に繋がりました。報告やレポートも非常に丁寧で、「ここまでやってくれるのか」と驚きの連続でした。
Q:導入後、どのような成果を感じていますか?数値的な成果や定性的な成果を具体的に教えてください。
三橋様:
定量的には自治体の案件が2024年には「3件」、2025年には「12件」、実際に受注となり、非常に大きな一歩となりました。
今でも、過去に繋がった自治体さんから定期的にご相談をいただける関係性を作ることができ、この事業における仮説検証としては良い成果を得られたと感じています。
定性的には、これまで選択肢になかった「外部の方との協働」という点でコミュニケーションの方法や、社内への認知(効率・効果が良い)という知見や感覚が得られたことが収穫ですね。
徳田様:
先ほど話にもありましたが、これまで弊社では“自前主義”でいろいろ賄っていたんです。
過去には電話営業も社内の人間で「一人〇件、〇日までに」という感じで手分けをしていたのですが、なかなかうまくいかないし、社員のストレスにもなっていたと思います…。
今回プロの方にお願いすることで、社内での電話営業による心理的負担からも解放されたのは大きいですね。
あと、最も驚いたのは「ナレッジの蓄積」に繋がったことです。資料作成法や顧客情報など、大学ノート4冊分もの詳細な情報が残り、「こんなに残していいのか」と思うほどでした。これは将来的に社内で営業を行う際の貴重な資産となり、今後の事業展開における幅も広がったと感じています。
また、プロの方の下で活動いただいている方については直接お会いすることはありませんでしたが、非常に丁寧な連携だったのでまさに「同じチームで一緒に働いているような感覚」で、営業経験のない私にとっては特に心強かったです。困った際の相談や商談への同席など、プラスアルファのフォローも多々あり、とても勉強になりました。
Q:外部人材の方を活用していて、どのようなメリットを感じましたか?
三橋様:
新規事業は将来が見通せないため、新規事業と外部人材の活用は非常に相性が良いと感じました。
また、人材採用の観点からもメリットがあり、従来の採用に伴う「うまくいかなかったら人材をどう再配置すればよいか…」というリスクがありません。プロクルなら成果が見えれば継続でき、効果的なリソース活用が可能です。BtoB事業を伸ばしていきたい現在の状況において、外部人材活用は事業の選択肢を大きく広げてくれたと認識しています。
Q:最後に、外部人材活用を検討している企業に対して、アドバイスやメッセージはありますか?
三橋様:
今回の経験を通して、外部の方とうまく連携できれば効率も効果も良いという知見が溜まったため、今後も外部人材を上手に活用していきたいと思っています。
ただし、その前に「何を求めているか」を明確にすることが重要で、私たちのように「一緒に伴走してくれるパートナー」を求めるのであれば、プロクルは非常に有効なサービスだと感じています。
徳田様:
今回は「自治体への営業」というご相談でしたが、プロクルさんであれば案件に合う良い方を的確に紹介してくれると思います。また、「外部の人だから」と距離をとるのではなく、「ちゃんと目線を合わせて、内部の人材と同じようなコミュニケーションで向き合う」ことで良い関係が築けると思います。