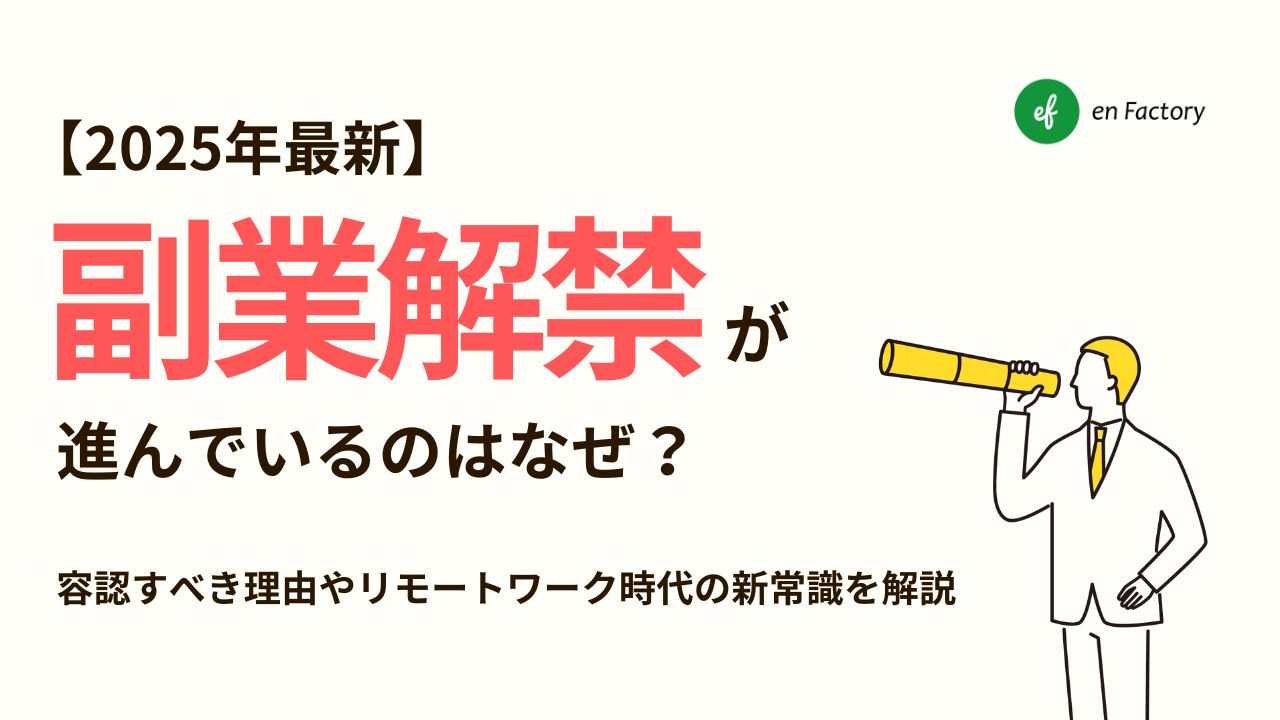終身雇用が崩壊しつつある昨今、多くの企業から注目されているのが副業解禁です。厚生労働省や経済産業省など、政府も積極的に副業解禁を推進しています。
しかし、「なぜこれほど副業の解禁が注目されているのかわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際、副業解禁にはメリットとデメリットの両方が存在するため、昨今の副業解禁の流れに対して疑問を覚えるのも無理はありません。
そこでこの記事では、副業解禁が注目されている理由を徹底的に解説。副業解禁に成功した企業事例や、副業解禁を行う際に実施しておくべき対策も紹介するので、副業解禁でお悩みの方はぜひ最後までお読みください。
目次
副業とは?
副業とは、本業と並行しながら行う別の仕事のことを指します。本業で身につけたスキルを活かした別の仕事を行うケースもあれば、SNS運用などの本業とは全く関係ない仕事を行うケースもあるなど、副業の内容は多種多様です。
これまでの日本企業では、「副業は本業をおろそかにしてしまう」という考え方から、こうした副業を原則として禁止することが一般的でした。しかし現在では、こうした価値観が大幅に転換しつつあります。
実際に、2018年の「副業元年」以降、副業を容認する企業は急激に増加しました。経団連が実施した調査によると、副業を容認する企業の割合は下表の通りです。
| 年度 | 副業の容認率※ |
| 2018年 | 41.4% |
| 2019年 | 46.0% |
| 2020年 | 50.6% |
| 2021年 | 60.9% |
| 2022年 | 83.9% |
※社員数5,000人以上の企業のうち、副業を「認めている」「認める予定」と答えた企業の合計
参考:一般社団法人日本経済団体連合会 副業・兼業に関するアンケ―ト 調査結果
こうしたトレンドは、今後もしばらく続くと予測されています。
副業解禁が注目されている背景
副業解禁の流れが加速していることがわかりましたが、どうしてこれほどまでに副業解禁が注目されているのでしょうか。結論から申し上げると、副業解禁が注目されている背景は次の3つです。
- 終身雇用の崩壊
- 政府の方針
- 副業に対する関心の増加
3つのポイントについて、順に詳しく解説します。
終身雇用が崩壊しつつある
ビジネス環境の複雑化が進んだ現代では、高度経済成長期に普及した日本型の終身雇用制度を維持することはほとんど不可能です。
これまでの日本では、新卒一括採用で優秀な学生を囲い込み、「自社で通用する人材に育て上げる」という価値観が一般的でした。一方、グローバル化やIT化によって変化の激しさが増した現在、こうした「社員を育て上げる」ことの効率は相対的に下がっています。社内で身につけたスキルや知識が、10年後や20年後も有効かどうかはわからないからです。
こうした状況では、社員が主体的に自分のスキルや知識を磨き続けることが求められます。その手段として注目されているのが、まさに副業なのです。
副業を通じて社外の環境を知ることが社員の成長につながり、ひいては自社の競争力向上につながると考える企業が増えてきています。
政府も副業解禁を推進している
政府の姿勢も、副業の容認が進んだ背景の一つです。副業に関する近年の政府の動向は、次のようになっています。
| 2017年 | 厚生労働省が「働き方改革実行計画」を公表。多様な働き方を実現する手段として副業に言及。経済産業省も「兼業・副業を通じた創業・新企業創出に関する研究会」の報告書を公表。 |
| 2018年 | 厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表。副業解禁に際して必要な企業の対応などを示した。2020年と2022年に改訂。 |
| 2023年 | 厚生労働省が「副業・兼業の促進に関する取組について」を公表。副業や兼業の事例集を公表し、解禁の現状や労働時間の計算方法などを示した。 |
これらの動きからも分かる通り、政府は「働き方改革」の一環として、副業の普及促進を明確に打ち出しています。特に2017年から2018年ごろにかけてさまざまな動きがあり、この時期に副業を容認する企業が一気に増えました。
このような政策の背景には、副業の推進を通じて柔軟な働き方を実現することが、労働生産性の向上につながるという考え方があります。また、少子高齢化による労働人口の不足を補うという狙いも大きいです。
参考:厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドライン, 副業・兼業の促進に関する取組について
副業に興味を持つ社員が増えている
社員の副業に対する関心が年々高まっていることも、副業解禁が叫ばれる背景の一つです。特にZ世代と呼ばれるような若い世代ほど、こうした傾向が顕著にみられます。
株式会社みらいワークスが2025年に公表した調査によると、副業経験がない人のうち、「副業に興味がある」と答えた人の割合は28.1%に及びます。また、実際に副業経験がある人の割合は、次のような結果となりました。
| 30代 | 24.7% |
| 40代 | 17.8% |
| 50代 | 8.8% |
| 60代 | 7.9% |
出典元:株式会社みらいワークス (https://mirai-works.co.jp/ )
こうした調査からも分かる通り、若い世代ほど副業に高い関心を持っていることがわかります。実際、「副業ができるかどうか」を会社選びの基準の一つにする人もいるほどです。
副業に興味を持つ社員の心をつかむためにも、副業の容認は企業にとって重要な施策となりつつあります。
従業員が副業に興味を持つのはなぜ?
先ほど副業に興味を持つ従業員が増えていると述べましたが、どうして副業に興味を持つ従業員が増えつつあるのでしょうか。
これにはさまざまな理由が指摘されていますが、大きく次の3点に集約されると言われています。
- 自由な時間が増えたから
- 待遇を改善したいから
- 仕事を気軽に探せるようになったから
従業員が副業に興味を持つ理由をさらに掘り下げていきましょう。
自由な時間が増えたから
働き方改革によって、社員が自由に使える時間が大幅に増えました。
例えばリモートワークの普及によって、これまで通勤に費やしていた時間が有効活用できるようになりました。この時間を使って、自宅でも始められる気軽な副業に挑戦してみたいと考える従業員が増加しています。
また、残業時間の削減も重要な背景の一つ。長時間労働の是正によって過度な残業が減り、その分の時間を自宅での副業に活用する従業員が増えてきています。
待遇を改善したいから
現在の待遇を改善したいという考えから、副業を始める従業員もいます。
企業によって差がありますが、日本企業ではまだまだ年功序列の評価制度が根強く残っています。こうした環境では、「本業でなかなか昇進や昇給ができそうにない」と考える従業員が増えるのも無理はありません。
実際、独立行政法人労働政策研究・研修機構が2023年に公表した調査では、副業を始める理由として「収入を増やしたいから」が54.5%で1位となりました。2位の「1つの仕事だけでは収入が少なくて、生活自体ができないから」も38.2%にのぼっており、多くの従業員が収入面を理由に副業を検討していることがわかります。
独立行政法人労働政策研究・研修機構 副業者の就労に関する調査
仕事を気軽に探せるようになったから
IT化の進展によって、副業の機会を見つけることが格段に容易になりました。副業探しに特化したサイトやサービスも多数登場しており、誰でも簡単に副業を探すことができるようになってきています。
こうした副業をマッチングするプラットフォームはオンライン上で誰でも気軽に利用できるため、利用時の心理的なハードルが低い点も特徴。「気軽な気持ちでやっていたのに、気がついたら本業の収入に匹敵していた」というケースも決して珍しくありません。
副業を解禁した企業事例3選
ここからは、副業解禁に成功した企業事例を3つ紹介します。実際に副業解禁に踏み切った企業の事例を通じて、副業解禁の効果を確認していきましょう。
なお、これらの事例は弊社エンファクトリーのご用意する「副業解禁ガイドブック」でさらに詳しく解説しています。本格的に副業解禁を検討している方は、ぜひこちらのガイドブックをご覧ください。
東京海上日動火災保険株式会社
東京海上日動火災保険は、イノベーションの創出や社員の成長促進などを目的として、2021年に副業解禁を発表。16,296名の社員全員を対象に、人事部による許可制で副業解禁を実現しました。
本事例では、副業申請時に社員は以下のような内容を申請しています。
- 副業の形態(雇用・非雇用)
- 業務内容
- 副業の内容が1ヶ月30時間以内か
副業先には大きな制約を設けていませんが、保険業に抵触しないことを前提としつつ、いくつかの承認基準を設けています。
制度の導入から4ヶ月足らずで副業実施者数は81名に達し、社内全体で「挑戦」に対する機運が高まるなどの効果が出ました。
コニカミノルタ株式会社
コニカミノルタ株式会社では、2018年に副業を解禁。オープンイノベーションの創出や新しい価値創造、優秀な人材の確保などを期待して、人事部による許可制で副業解禁を行いました。
副業申請時には、以下の項目を提出する必要があります。
- 副業の内容(会社名など)
- 副業に取り組もうと思った動機
- 副業を通じてコニカミノルタにどのような貢献ができるか
解禁後、副業を実施する社員の数は2019年時点でおよそ60名に到達。主体性の向上やネットワーキング、社内交流の促進など、さまざまな効果が見られたそうです。
カゴメ株式会社
カゴメ株式会社では、多様性や主体性の促進などを目的として、2019年に副業解禁を実施しました。本事例でも、人事部による許可制で副業を認めています。
副業申請時の申請内容は、主に次の通りです。
- 副業の形態
- 内容
- 1ヶ月あたりの実施予定時間数
副業先に関しては、大きな制限はありません。「同業での副業が社員の成長につながることもある」という考え方から、同業他社での副業も場合によっては可能です。
制度の導入後には、生産性向上や労働時間の削減といった多くの効果が見られました。制度の導入時から80件程度(2023年10月時点)の風行申請がされているそうです。
副業を解禁する企業が必ず行うべき対策
副業解禁には多くのメリットがありますが、同時にいくつか注意点が存在することも事実。
ここからは、副業を解禁する企業が必ず行っておきたい対策を3つ解説します。副業解禁のメリットを最大限に引き出すため、ぜひ意識しておきましょう。
なお、ここから解説する対策方法は、弁護士監修の「副業解禁ガイドブック」でも詳しく説明しています。ぜひ、下記のリンクから資料をダウンロードしてください。
就業規則を整備する
副業を解禁する際は、就業規則を整備しましょう。
まず、現在の就業規則に「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」といった記載がある場合、修正が必要です。例えば、「勤務時間外において、他の会社等の業務に従事できる」といった記載に変更するか、より詳しく許可の手続きや条件を明記する必要があります。
副業を許可しないケースを設ける場合には、それらの条件を就業規則内に明記することも可能です。
ルールを明確化する
副業を解禁する際は、次のようなルールを明確化する必要があります。
- 事前申請の内容と手順
- 許可制の場合は、承認基準と承認フロー
事前申請の内容としては、副業の内容や勤務時間、副業へ取り組もうと思った動機などが一般的です。前述した事例もぜひ参考にしてください。
承認基準としては、以下のような項目が設けられることが一般的です。
- 利益相反の回避
- 会社ポリシーの遵守
- 健康と安全の確保
- 守秘義務の遵守
必要に応じて、これらに関する誓約書の提出を求めることもできます。なお、副業の状況を把握するため、定期的に副業状況を報告してもらう体制を作ることもおすすめです。
社員の健康確保を徹底する
副業解禁のデメリットとして、社員の労働時間の長期化が指摘されています。社員の健康を維持するためにも、労働時間の管理の徹底を心がけましょう。
副業に関連する労働時間の計算方法は、現在も議論が進んでいます。2025年時点では、主に以下の方向で検討されていることを理解しておきましょう。(ただし、法的に時間管理の義務が生じるのは「雇用」による副業のみ)
| 労働時間の通算ルール | 日・週単位ではなく、月単位のみでの把握を求める方向で検討中 |
| 割増賃金の計算方法 | 労働時間は通算せず、各事業所で個別に計算する方向で検討中 |
| 健康確保の考え方 | 賃金計算のための労働時間と健康確保のための労働時間を分けて考えることを検討中 |
まとめ
2025年に入り、副業解禁の流れはますます加速しています。先の見えづらいVUCAの時代に欠かせない取り組みとして、今後も副業への社会的な関心は高まっていくでしょう。
しかし、副業解禁にはなかなか手間がかかるのも事実。この記事の最後で解説したように、就業規則から運用ルールの策定、社員の健康確保など、考えるべきことは多岐にわたります。
そこで、いきなり副業解禁に取り組むのではなく、まずは社内で別の業務に取り組む「社内副業」から始めてみるのはいかがでしょうか。社内副業であれば、副業のメリットである社員の成長やイノベーションはそのままに、副業の効果を実感することができます。社員としても、外部で雇用されるよりハードルが低いため、気軽に取り組みやすいです。
弊社エンファクトリーでは、社内副業を支援するサービスを実施しています。社内副業にご興味をお持ちの方は、ぜひ下記のリンクから詳細をご覧ください。