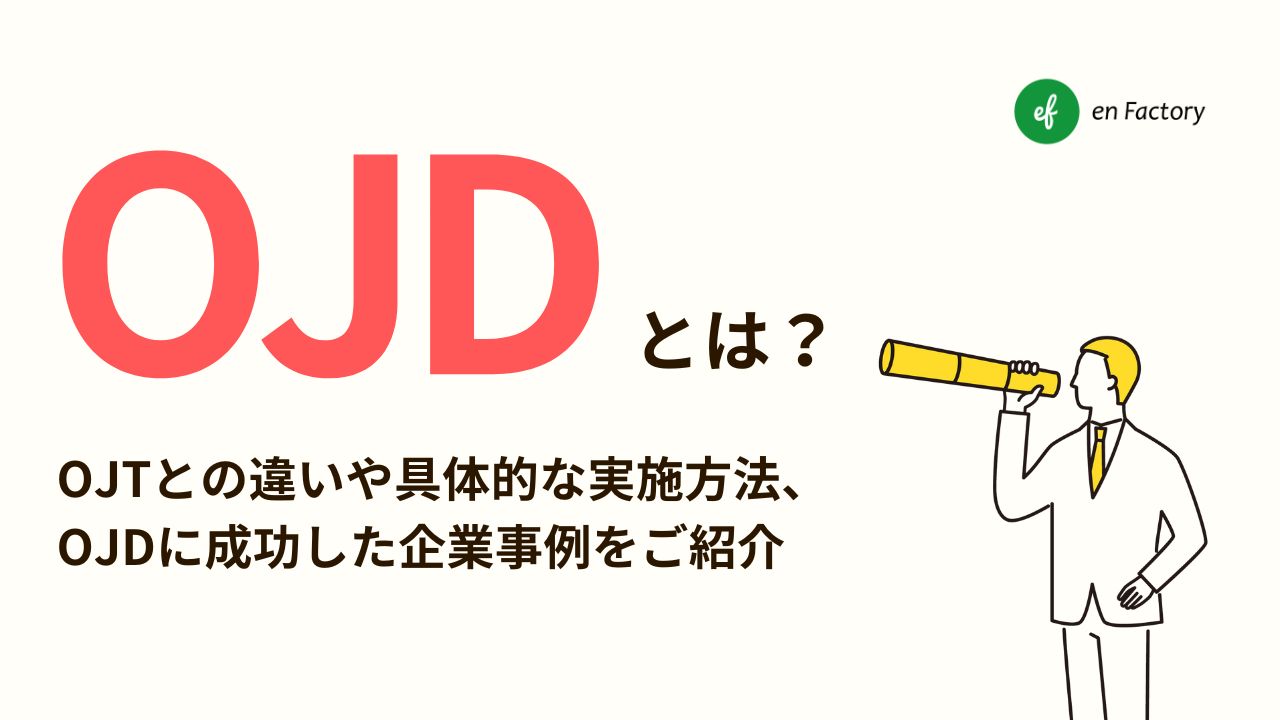デジタル化やグローバル化が進む現代のビジネス環境において、人材育成のあり方に課題を感じている方も多いのではないでしょうか。こうした中で注目されているのが、「OJD」と呼ばれる新たな取り組みです。これまで主流だったOJTとは異なり、OJDでは長期的かつ多角的な取り組みを重視します。
本記事では、OJDの定義やOJTとの違い、具体的な進め方を詳しく解説します。企業での導入事例も紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
目次
OJDとは?
OJDとは、実際の業務を通じて社員の長期的な能力開発を促す手法です。「On-the-Job Development」の頭文字を取った略語で、従来のOJTよりも幅広い活動に取り組みます。
OJDでは、計画的に能力開発へ取り組む点が最大の特徴です。新入社員からベテラン社員まで幅広く行われる取り組みで、具体的な実施方法も多岐にわたります。
OJTとの違いは後ほど詳しく解説しますが、OJDの方が長期的で幅広い取り組みであるという点が主な違いです。
OJDの概念が浸透した経緯
OJDは2000年代後半から徐々に人材育成の現場で注目されるようになり、VUCA時代に入って一躍脚光を浴びました。OJDが浸透した経緯は、主に次の2つです。
- ビジネス環境が急速に変化した
- OJTだけでは対応しきれない複雑な課題が増えた
昨今は、グローバル化やIT化によってビジネス環境が目まぐるしく変化しています。こうしたビジネス環境では、一度身につけたスキルがいつまでも役に立つとは限りません。例えば昔は貴重だった暗算力が電卓に取って代わられたように、現在重要視されている多くのスキルも数十年後にはAIによって代替されている可能性があります。
そこで、個々のビジネススキルを磨くのと同時に、社員のマインド面も磨こうという考えが主流になりました。例えば変化への適応力や学習能力を伸ばすことで、時代に取り残されない人材を育てることができます。
OJDは、こうした「人材開発」を目指すために生まれた発想です。OJDに取り組むことで、長期的に価値を創出し続ける人材を育てることができます。
OJDとOJTの違い
OJDとOJTの違いは、下表の通りです。
| OJD | OJT | |
| 育成スパン | 長期的 | 短期的 |
| 重視する内容 | スキル・マインド全般 | 業務スキル |
OJDとOJTの違いについて詳しく見ていきましょう。
育成スパンが長期的か短期的か
OJDとOJTの最大の違いは、育成スパンです。
OJTは、主に短期間での業務スキル習得を目的としています。通常は数週間〜数ヶ月程度の期間で完了し、指導内容も基礎スキルの習得という側面が強いです。
一方、OJDは社員の長期的な成長を見据えた育成手法で、数ヶ月〜数年という長いスパンで実施されます。複数の実施方法を併用することも多く、将来のキャリアを見据えた指導を行う点が特徴です。
業務スキル重視かマインド重視か
重視する内容も、OJDとOJTの違いの一つです。
OJTでは、主に業務遂行に必要なスキルや知識の習得に焦点を当てます。例えば営業部門では、商品知識や提案資料の作成方法を一通り身につけることが典型的なOJTの目標です。
一方でOJDでは、社員のマインドとスキルの両面にフォーカスします。例えば営業職でOJDを実施する場合、単に商品を売るだけでなく、顧客の潜在的なニーズを理解した上で、長期的な関係性を構築できるようになることを目指すのが特徴です。
OJDの実施方法は主に5通り
OJDにはさまざまな実施方法がありますが、代表的な手法は以下の5つです。
- プロジェクトアサイン
- メンタリング・コーチング
- ジョブローテーション
- 社内副業
- 越境学習
OJDの具体的な実施方法について詳しく解説します
なお、実際にOJDへ取り組む際は、これらを複数組み合わせるのも手です。自社の状況や人材育成の目標に応じて、最適な育成プランを考えてみてください。
プロジェクトアサイン
プロジェクトアサインとは、社員を普段と異なるプロジェクトに配置する方法です。新規事業の立ち上げや業務改善プロジェクトといったチャレンジングな課題に取り組むことで、スキル面・マインド面の双方での成長を促します。
なお、プロジェクトアサインを行う際は、社員にとって「少し背伸びすれば追いつける」程度の役割を与えることが重要です。
人間の成長には、以下の3つの領域があると言われています。
- コンフォートゾーン
- ストレッチゾーン
- パニックゾーン
1つめのコンフォートゾーンは社員にとって居心地が良い領域ですが、いわゆる「ぬるま湯」のような状態で、スキル・マインド面での成長が期待できません。3つめのパニックゾーンは社員にとって過度な負担がかかるため、こちらもかえって成長が阻害されてしまいます。
社員にとって程よい負荷がかかる「ストレッチゾーン」に配置することで、プロジェクトを通じた大きな成長が期待できます。プロジェクトアサインを行う前に社員の能力を正しく把握した上で、プロジェクトの進行中も随時フォローすることが大切です。
なお、プロジェクトアサインを行う際にぜひ理解しておいていただきたいのが、「タフアサインメント」という考え方です。タフアサインメントに関しては、次の記事で詳しく解説しています。
タフアサインメントとは?リーダーを育成する実践機会の作り方と事例、失敗しないためのポイントを解説
メンタリング・コーチング
メンタリング・コーチングは、先輩社員が後輩社員の成長をサポートする手法です。それぞれ、次のような指導を行います。
| メンタリング | 対話を通じて後輩社員の悩みを引き出し、解決を支援する |
| コーチング | 相手に質問を投げかけながら後輩社員の目標達成をサポートする |
メンタリングとコーチングは、ともに社員の自主性を尊重する育成手法です。例えば新任の管理職が部下のマネジメントに悩んでいる場合、先輩社員は「こうしなさい」と指示するのではなく、「その部下の行動の背景にはどんな事情があると思いますか?」「あなたならどんな支援が欲しいと思いますか?」といった質問を投げかけます。
自らで問題を解決してもらう能力を養うという点において、メンタリングとコーチングはどちらもOJDにうってつけの手法です。
ジョブローテーション
ジョブローテーションは、社員をあえて異なる部署や職種へ定期的に配置転換する手法です。幅広い業務経験を得ることで、社員の視野を広げるとともに、会社全体への理解を深めてもらうことができます。
ジョブローテーションも、OJDを実現する方法の一つです。社員は普段と異なる業務へ取り組む中で、変化への適応力や柔軟な考え方を身につけることができます。
ただしジョブローテーションを実施する際は、受け入れ部門や社員の負担を考慮しましょう。ジョブローテーションが「配置転換の言い訳」にならないよう、事前に社員と部門双方の意向をよくすり合わせておくことが大切です。
社内副業
社内副業も、OJDを実現する手法の一つです。
社内副業では、本来の業務に加えて他部門の業務や新規プロジェクトへ一定期間参加します。例えばエンジニアが営業部の業務効率化プロジェクトへ参加したり、人事が新規事業の採用戦略立案に協力したりするのが社内副業の一例です。
社内副業を導入すると、次のような効果が期待できます。
- スキルアップ
- 幅広い視野の獲得
- 社内のコミュニケーションの活性化
最近では、社外での副業の代わりに、社内副業を導入する企業も多いです。
なお弊社エンファクトリーでは、社内副業の導入を検討している方に向けたガイドブックもご用意しております。社内副業をご検討の方は、ぜひ下記から資料をご覧ください。
越境学習
越境学習は、ベンチャー企業やスタートアップ企業で3ヶ月〜6ヶ月程度かけて研鑽を積む手法です。異なる企業文化や働き方に触れることで、社員の視野を大幅に広げ、適応力の強化やキャリア自律を促します。
越境学習の最大のメリットは、留学先の企業へ深く入り込むことができる点です。単に文化や業務を「体験」するのではなく、留学先企業の一員として真剣に課題解決に取り組みます。
期間も3ヶ月〜6ヶ月程度のことが多く、長期の取り組みを重視するOJDとも相性が抜群です。
エンファクトリーでは、はじめて越境学習を実施する企業に向けたガイドブックもご用意しております。越境学習をご検討の方は、ぜひ下記の資料を参考にしてください。
社内副業でOJDに成功した事例
エンファクトリーでは、さまざまな方法でOJDを支援してまいりました。ここからは、それらの中から特に参考となる事例をピックアップしてご紹介します。
まず紹介するのは、社内副業を通じてOJDに成功した事例です。社内副業の進め方や効果などを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
コクヨ株式会社
オフィス家具・文具大手のコクヨ株式会社。同社独自の取り組みとして、社内副業制度「20%チャレンジ」を導入しています。
「20%チャレンジ」とは、「普段の業務時間の20%程度を活用して、自分の部署とは異なる部署の業務へ参画する」という制度です。各部署から「このようなテーマで一緒にやってくれる人を探している」という求人を出してもらい、それぞれの社員へ自由に応募してもらうという形式を取っています。
スタートから5年以上が経過しますが、これまでに合計400名程度の社員が20%チャレンジへ参加しました。参加者からは、「充実感があった」「新しい仕事の進め方や考え方を身につけられた」などと数多くのポジティブな声が上がっています。
時間配分などでいくつかの課題はあるものの、社員一人ひとりの「やりたいこと」をすくい上げることができる仕組みに大きな効果を実感しているそうです。
本事例の詳細は、下記の「はじめての社内副業ガイドブック」から詳しくご覧いただけます。
三井住友海上火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社では、2021年7月から社内副業制度を運用しています。同社の取り組みは、主に以下の2つ。
- プロジェクトチャレンジ
- Meetup
プロジェクトチャレンジは、現場と本社の社員が協力しながら、1〜6ヶ月程度で成果物を出す取り組みです。Meetupでは、特定のテーマに対して関心を持った社員が集まり、1〜2時間程度でフランクに意見交流します。
どちらも社員の自主性に委ねた取り組みで、希望者のみがエントリーする公募型で運用しているのが特徴です。弊社エンファクトリーが提供する公募システム「Teamlancerエンタープライズ」には合計2,000名以上が登録し、これまでに約400名が実際に社内副業へ挑戦しました。
越境学習でOJDに成功した事例
ここからは、越境学習を通じてOJDに成功した事例を紹介します。いずれも、ベンチャー企業やスタートアップ企業へ3〜6ヶ月間留学した事例です。
株式会社オリエントコーポレーション
株式会社オリエントコーポレーションの樋口様は、「自分のスキルが社外で通用するのか確認したい」「変革マインドが機能しているか確認したい」といった思いから、エンファクトリーの実施する異業種チーム活動型の越境学習プログラム「越境サーキット」への参加を決めました。
本事例では、酒造を手掛ける企業で3ヶ月の越境学習へ取り組んでいただいています。チームメンバーにはさまざまな特徴を持った人がいましたが、樋口様が率先して「対話の橋渡し役」となることで、チーム全体のスムーズな協働を実現できたそうです。
異業種の人と交流した効果について、インタビューでは次のようにお答え頂いています。
❝全く異なる業種の方々と接することで、その会社では当たり前のプロセスや用語について知らないことに気づくことができました。ミーティングの後に一人で調べてみると、理解が深まりましたし、新しい視点を知ることができ、物事を異なる角度から見る大切さに気づかされました。❞
越境学習を通じて、自己理解の促進や新しい視点の獲得に成功した事例です。樋口様のインタビュー全文は、下記のページからご覧いただけます。
越境サーキット参加者インタビュー「越境で広がる可能性:自己発見と周囲への好影響」
三井住友海上火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社の赤井様。普段の業務内で他業種の方と深く関わる機会が少ないという思いから、越境サーキットへ参加されました。
越境学習へ参加する前、赤井様は「自分は過度に自己犠牲してしまう」と感じていたそうです。しかし、越境学習へ参加したことで、「自分の得意分野は全力を尽くし、そうでない分野では他のメンバーに気持ちよく任せる」ことの大切さを感じるように。それぞれの得意不得意がある環境だったからこそ、マインド面に前向きな変化が生まれました。
インタビューでは、越境学習による価値観の変化について次のようにお答え頂いています。
転職を3回経験している方や、会社内でいろんな部署を転々としている方、人事の方など、普段は全く会話しないような職種の方と話をし、活動を進める中で、自分が今いる会社や部門にとどまることが必ずしも必要ではないと感じるようになりました。転職や異動も選択肢として十分に考えられることを知り、視野が広がったと思います。
本事例の詳細は、以下のインタビュー記事からご覧ください。
越境サーキット参加者インタビュー「チームワークで学んだ自己理解と変化」
まとめ
OJDについて、OJTとの違いや具体的な実施方法を詳しく解説しました。
ビジネス環境が激しく変化するVUCAの時代では、単に「目の前の業務をこなすスキルを身につける」だけでは不十分です。今後の変化を見据えた上で、さまざまなスキルを身につけるための学習力や適応力を伸ばしていく必要があります。
OJDは、そうした「学ぶ力」「適応する力」を身につけるための人材育成手法です。従来のOJTに限界を感じている方はもちろん、そうでない方もぜひ本記事をきっかけにOJDの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
本記事が、OJDを導入する際のお役に立てれば幸いです。